こんにちは。
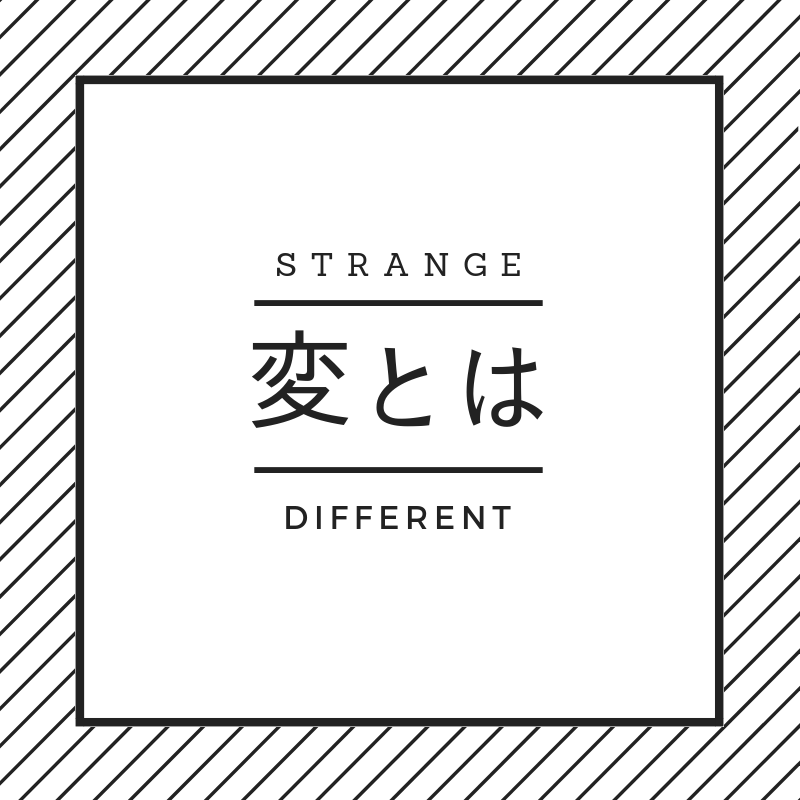
友達数人と車でドライブに行くときに必ずやるのが音楽を流すことです。それぞれがスマホを持ちより、交代で車のBluetoohに接続してスピーカーから好みのミュージックを流すのです。
僕も、自分の番になったらスマホに入っているお気に入りの音楽を流します。ところが、その際に友達から必ず毎回言われることがあります。それは、僕が流す曲が“変なものばっか”ということです。
僕が気に入っている好きな曲を流すと、周りの友達は必ずと言っていいほど「なにこの変な歌?」「ほんと変な曲が好きだね」と言ってきます。
たしかに僕は、曲調が独特な曲だったり、極端に特定の主張が強い曲だったり、北○鮮関係の曲だったり、とても大衆向けとは思えない独特な音楽をよく聞きます。しかし、それを一言で「変なもの」と指定してしまうのはどうなのでしょうか。
目次
「変な歌」は存在しない
そもそも歌は人間が作り出す“芸術作品”の1つです。芸術作品とは、アーティスト(製作者)が作りたいと思ったものを自由に作るものなのですから、それに正解も不正解もありません。すなわち“変なもの”とされる作品は存在しないのです。
たしかに、ある程度の範囲の型にハメられた大衆向けの音楽はあります。しかしだからと言って、その型にハマっていない音楽が“変なもの”と位置づけられるのは間違っています。音楽もそもそもは芸術の1つなのですから。
「変」は寛容さの欠如
一般的に人が特定の対象物を「変である」と感じる要因は、それが周りと違っていたり、異なっていたりすることが挙げられます。つまりは、非常に主観的な感情とも言えます。
靴のまま家に上がることを「変だ」決めつけたり、挨拶でキスを交わすことを「変だ」と考えたりすることは、異文化を理解していないからですよね。
自分がこれまで経験してきたものや、自分が普通(常識)と感じるもの以外に接触したとき、人は少なからずアレルギーを起こすものです。しかし、すぐにそれを理解すること、受け入れることで、そのアレルギー反応を無くしていくことができます。
逆に、アレルギー反応がでたらそれを全力で拒絶してしまう人、すなわち不寛容な人は、その対象物を「変なもの」と決めつけシャットアウトしてしまうのです。
違っていること=「変」ではない
マジョリティとは違った性質を持っている人やモノは、必ずしも「変なもの」であるとは限らないのです。そうした少数なもの、マイノリティなものを「変なもの」と決めつけることは差別にも繋がります。
同性同士で愛し合うことは、一般とは違ったものではありますが、決して「変」ではありません。それも一つの愛の形ですよね。
一般とは違ったものを「変なもの」と表現するのは簡単ですが、それはポジティブな表現ではありませんし、人を傷つけることにも繋がってしまうのです。少数だから間違っている、ということは決してありません。
学校教育の影響
学校教育では“型にハマる”ための訓練を行います。全員が同じ服を着こなし、同じタイミングで移動し、決められた範囲で物事を考えるように教わります。型の範囲以外の振る舞いをすることは基本的に許されません。独特な音楽が昼休みの放送で流されることはほぼありませんよね。
その結果、その教育を受けてきた人間は、人とは違っていること、一般的ではないものと接触したときに、それを「変なもの」と考えてしまうようになってしまうのではないでしょうか。
ただ、型にハマることは必ずしも悪いことではありません。社会では、型にハマった方が楽だし、うまく行くことがありますからね。これは本当に難しい問題だと思います。
まとめ
- 変な歌というものは存在しない。なぜなら、歌は芸術であり、芸術には正解も不正解もないからである。
- 何事も「変」と決めつけてしまうことは、自分の考える常識とは違うものを受け入れようとしない、寛容さに欠けた行為である。
- 学校教育で型にハマることを教わり続けた結果、周り一般とは違う人・モノを「変」と捉えてしまう人が現れてしまうのではないか。
一人一人が、自分とは違うものを認めていく寛容さが、これからの時代には益々求められてきます。これは気を付けていきたいポイントですよね。自分も含めて、迂闊に「変」と決めつけてしまわないよう気を付けていきたいものです。
最後まで見てくれてありがとうございます。